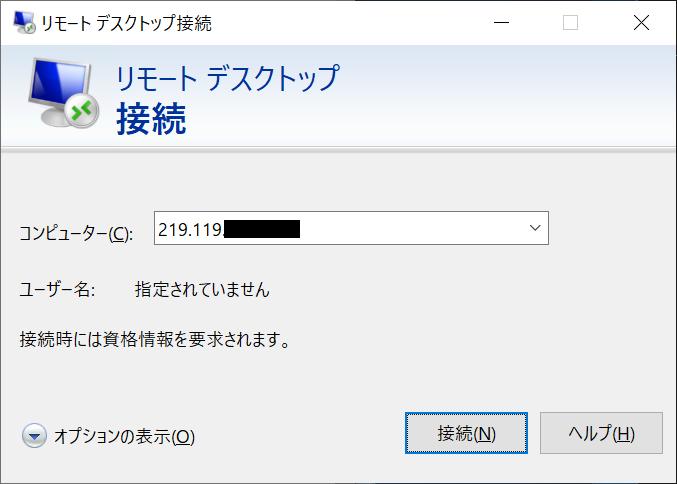俳優の市毛良枝さんは脳梗塞をきっかけに13年近く、母を介護しました。最初は「一人娘だから私が頑張るしかない」という気持ちが強かったものの、徐々に周りの人を頼るようになっていきました。家族以外の人が介護に関わる大切さを実感したと言います。どんな心境の変化があったのでしょうか。
【全力投球しない介護 母が残してくれたものは】市毛良枝さんインタビュー(下)はこちら
母の看病でも実感した自然の力
市毛さんの母は2004年、2005年に脳梗塞(こうそく)を発症。ちょうど仕事が一段落し、趣味の山登りに没頭したいと思っていた矢先、母の介護中心の生活が始まりました。病院で同室だった患者さん親子や自然の存在に助けられながら、親の老いに向き合いました。
母は2005年1月に2度目の脳梗塞になりました。この入院中にベッドから転落して、大腿骨頸部(けいぶ)という足の付け根部分の骨が折れる大けがをしたのですが、脳梗塞の治療で血液をさらさらにする薬を使っていたので、すぐには骨折の手術ができませんでした。10日間ほど寝たきりだったため、一時的にですが、私のことが誰かもわからなくなりました。
このとき6人部屋だったんですが、同じように親御さんに付き添っていた「娘たち」に色々と学ばせてもらいました。ある娘さんは、お母さまに政治や選挙のことなど色々なことを話しかけていましたね。
私は隣でそれを聞きながら、内心では「お母さまはほとんど意識がないし、あんな風に話しかけてもわからないよね」と思っていました。それでも、その方は毎日毎日、テレビを見せたり、「小泉(純一郎)さんがこう言っているよ」と話したり、車いすで外に連れて行ったりしていました。
そうしているうちに、そのお母さまにだんだん表情が出てきたんです。「懲りずに声をかけていれば、元気になっていく」ということを教えてもらいました。寒い時期でしたが、私も母を病院の庭に連れ出すようにしたら、母もどんどん元気になっていきました。太陽の光や風を感じ、花の香りをかぐ。自然に五感を刺激されることがとても大事なんだと感じました。
そういう自然の大切さは母の介護を通じて何度も実感しました。母はほとんど目を開けようとしないときでも、子どもたちが遊ぶ声や花のにおいは感じていて、そういうことがあった日はいつもより夕食をよく食べてくれましたから。
「あと数年しか生きられないかも」から始まった在宅介護
母はリハビリを経て半年ほどで、東京都内の自宅に戻りました。この家にはもともと私と母が一緒に住んでいましたが、完全な二世帯住宅だったので、互いに別々の生活を送っていました。坂の上にある戸建てで、半地下や中2階があってエレベーターもつけられない造りでした。「ここでは母と暮らせない」と思い、思いきってマンションを購入しました。
マンションでは、母のベッドのそばにパーティション(ついたて)とソファを置いて、私はそこで寝起きしました。「ねぇ」と呼ばれたらすぐに対応できるように、母の気配に全神経を集中させていたんです。
しばらくして母がだいぶ元気になったころ、私はつらかったソファでの寝起きをやめて別の部屋で寝ることにしました。でも、その初日にトイレに行こうとした母が転倒し、緊急入院してしまい、寝室を別にしたことをすごく後悔しました。
介護が始まったころは、「母はあと数年しか生きられないかもしれない」と何となく思っていたので、母中心の生活を送っていました。二人羽織みたいな生活で、外出は仕事に行く時くらい。私の仕事は時間が不規則なこともあって、介護保険制度のサービスは利用していませんでした。「私が1人で頑張るしかない」というような意識もありましたね。
母が恋しがった人々の暮らしの気配と自然の空気感
「さみしい」という母の希望で、マンションから再び一戸建てに戻った市毛さん親子。慣れ親しんだご近所さんがいること、人々の暮らしの気配や自然を感じられることが母にとって大切だったことに市毛さんは気づきます。

元の一戸建ては壊して売却するつもりでしたが、マンションに引っ越してしばらくすると、母が「帰りたい」と言うようになり、建て直すことにしました。「完成まで母は生きられないかもしれないけど、彼女が住める家を造れば、私が年をとっても帰れる家になる」と思ったんです。
「間に合うかな」と本当にどきどきしながらでしたが、間に合っちゃいましたね。「バリアフリーで、木とガラスをたくさん使った明るい家がいい」という母の願いをほぼかなえることができたので、母は「90歳を過ぎて、人生で初めて自分が住みたい家に住めた」ととても喜んでくれました。
実は、私は一戸建てよりもマンション暮らしの方が楽しかったんです。住民の方たちと色々なお話ができて、コミュニティーができていましたから。でも、母は何度も「さみしい」と言っていました。考えてみると、母は一人では出歩けないから、同じ階に住んでいる人と会うこともそんなにない。周りにたくさん人が住んでいても会えなければ、いないのと一緒だったんですね。
建て直した元の家に帰ったら、母はご近所に私の知らないお友達がいっぱいいたんです。私が近所を歩いていると知らない人から「私、あなたのお母さんとお友達なの」とよく声をかけられました。
通りすがりの人や子どもの声、風の音が聞こえるし、地面から上がってくる植物や土の匂いがしました。マンションでは2階に住んでいたのに、あまりそういったものを感じられなかったんです。外が全部コンクリートで固められているし、気密性が高いからでしょうか。母がさみしがっていた理由がよくわかりましたね。
「私、心配される側の人間になっちゃった」
母の介護が始まって5年近くたったころ、市毛さんの仕事は転換期を迎えていました。自分の心のバランスが崩れていることに気づいた市毛さんは、他人を頼り、介護保険サービスも利用するようになっていきました。
2008年ごろ、ちょうど私が58歳のころに、それまで立て続けにあった仕事が一段落しました。私自身の役柄が変わっていく時期でもあり、これまでお付き合いのあったテレビ局の方たちが退職される時期でもありました。それまでよりも母を介護できる時間は増えたものの、「介護だけに没頭したら、このまま居場所がなくなってしまうかもしれない」とすごく不安になりました。
そんなときに母が再び軽い脳梗塞になって入院。「父が亡くなったときと状況が似ている」と感じました。ちょうど入院した季節も同じ秋でしたね。死ぬなんて思いもしなかったのに、父は入院して2カ月ほどで亡くなりました。
「父のときと状況が似ている」という考えが浮かんだとたん、「私はこんなに一生懸命に母を介護しているのに、母がいなくなったら私のこれからはどうなってしまうのか。仕事も暇になって、帰る場所がなくなってしまう」とこわくなりました。
私と同じようにお母様を介護している友人がいたんですが、母が入院中にその友人のお母さまが亡くなりました。友人の喪失感を想像し、自分のことのように思ってしまいました。その友人にお悔やみのメールを送ったら、その文面を読んだ友人から「あなたのほうが大丈夫? 」と心配されましたね。そのとき、自分の心の状態が「おかしいかも」と気づきました。
母がリハビリでお世話になっていた病院の看護師さんも私の状況を心配してくれ、医療ソーシャルワーカーの方との面談を勧められました。その面談で3時間、私は泣き続けてしまいました。「あなたはあなたの生活をしてください。お母さまのことは、自分の生活をつくった上で考えましょう。残念ながら、お母さまは死んでいく人です。あなたが一緒に死んではいけません」というようなことを言われました。
母親の介護に専念するため芸能界を引退した俳優の清水由貴子さん(享年49歳)が自ら命を絶ったのもこの頃だったので、周りからは本当に心配されました。「私、心配される側の人間になっちゃった。もしこのまま仕事がなくなっても、自分の生活を立て直そう。必要なら人を頼ろう」と思いました。
まず、近所で色々な人に声をかけて、母の食事を作って、食べるのを見守ってくれる人を見つけました。それまでは私が仕事の合間に自宅に帰って食事を作って母に食べさせ、また仕事に戻っていましたが、それがなくなって本当に助かりました。その方には5年ほどお世話になり、その後、また別の方に出会って、食事の面倒をみてもらいました。
介護を始めたころは母のことは何でも自分がしなければという思いが強かったですね。母は、他人が家に入るのを嫌がるというか、恥ずかしいという感覚がすごく強い世代の人なので、「娘のあなたがやってよ」と思っていたと思います。私の仕事の時間が不規則で、人に事前にお願いしづらいのもあって、仕方なく自分一人でやっていた面もあります。
ただ、母は入院中に知り合った人などの言葉には比較的心を開く人だったので、「嫌だ」と言いながらも、デイサービスやショートステイに少しずつ行ってくれるようになりました。私自身も自分の年齢や仕事の将来を考えたとき、「人は必ず死ぬ。去っていく人の人生に自分の全てを注入してはだめ」というのがだんだんわかるようになりました。
そうやって2016年に母が亡くなるまでの5年くらいは在宅とショートステイをうまく組み合わせながら介護していました。そのおかげで、お稽古と本番で2カ月ほど予定が埋まる舞台にも出演することができるようになりました。
(撮影・伊藤菜々子)
(衣装協力)
・ジャケット、トップス、スカート=YUKIKO HANAI(株式会社花井 03-6738-4877)
・イヤリング=アビステ(株式会社アビステ 03-3401-7124)
・その他=スタイリスト私物
◇
<関連記事>
本プロジェクトは令和3年度介護のしごと魅力発信等事業(ターゲット別魅力発信事業)として実施しています。(実施主体:朝日新聞社・厚生労働省補助事業)